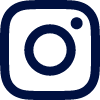もし、この地球上からインターネットという存在が消えていたとしたら——。
この想像は、私たちがいま立っている「歴史の分岐点」を静かに、しかし鮮烈に照らし出します。インターネットは単なる通信技術ではなく、人類の営みを根底から組み替えた“文明装置”であり、今日では空気や水と同じく、国家を支える基盤インフラとなりました。
行政、政治、経済、産業、教育、医療、そして私たち国民生活。そのすべてが、インターネットを前提とした構造へと再編されました。もしインターネットが存在しなかったなら、これらはまったく異なる姿をしていたはずです。それは単なる“便利さの欠如”ではなく、国家運営そのものが別次元の形態であったはずだ、ということです。
インターネットは、自由なアクセスと分散的アーキテクチャーが基本で、知識の共有、創造の連鎖、イノベーションの加速を可能にしました。一方で、サイバー攻撃、詐欺、偽情報など、国家の安全保障や社会秩序を揺るがすリスクも同時に顕在化させました。
また、巨大プラットフォーマーの台頭は世界の富の流れを根底から変え、“デジタル基盤を持つ国”と“持たざる国”の差は、単なる経済格差を越えて、国家の競争力そのものに直結する時代へと突入しています。
では、我が国・日本はどうか。残念ながら、1990年代のインターネット革命のインパクトを十分に読み取れず、その後の停滞を招いたことは否めません。そして今日においてもなお、変革のスピードに追いついているとは必ずしも言えません。法制度、行政手続き、データガバナンス——多くの領域で、いまだ“インターネット以前の常識”が影を落としているのが現実です。縦割りに固定化された行政システム、散在するデータ、時間ベースの労働慣行によって疲弊する現場、民間のイノベーションが行政に到達するまでの途方もない時間差。この構造を温存することは、インターネットなき世界線を、再び自ら選び取るに等しい行為です。このままでは、日本の未来を拓くことはできません。
いま必要なのは、“デジタル化の導入”といった表層的な改善ではありません。求められているのは、国家運営のOSそのものを更新し、日本社会全体のマインドセットを刷新することです。スピードと透明性を前提とするガバナンス、官民がデータを共有する「Digital Public Goods」の思想、AI・クラウド・サイバーセキュリティを国の基幹インフラとして位置づける覚悟——これらを同時並行で進めなければ、日本の競争力は世界の潮流から確実に取り残されます。
重要なのは、技術の細部ではありません。技術が社会を変えるのではなく、社会が技術を受け入れる器をつくれるか。テクノロジーを、日本の歴史・文化・価値観と調和させながら社会実装できるか。ここにこそ、日本のデジタル政策の核心があります。
インターネットのない世界を想像するということは、“インターネットのある世界にふさわしい新しい国家像”を構想するということです。私たちは、日本の文化と伝統を尊重しつつ、未来の社会基盤をどう設計するのかという問いを避けてはなりません。
自民党デジタル社会推進本部長として、私はデジタル技術を単なる効率化の手段と捉えず、
「国家の再設計」を実現するための原動力として位置づけ、日本らしいデジタル化、そしてテクノロジーの社会実装をさらに加速させる法律・制度の整備に全身全霊を尽くしてまいります。未来は、選択の積み重ねによってしか拓けません。私たち自身の決断で、インターネット時代にふさわしい新たな日本の姿を創り上げていく——その使命を、私は強い覚悟をもって担ってまいります。
#平井卓也